
Waldorf Microwave XTk
- 2009/11/15
Waldorfと言えば、近年ではblofeldとともに見事に復活したドイツのシンセサイザーメーカーです。Waldorfの歴史は、第2回のオフィシャルレビューで紹介したので、今回はこちらのMicroWaveXTkの紹介を中心に、レビューします。

MicroWaveXTシリーズは、ラック型の音源XTと、鍵盤付きのXTkの2種類があります。
もともと、このMicroWaveXTは、MicroWaveシリーズの3世代目となります。

ウェーブテーブル方式としては、最高峰のモデルとしてTheWaveという小室哲哉氏や浅倉大介氏などが愛用していた巨大なシンセサイザーがありますが、世界的にも流通が少ないためここでは説明を省きます。
一番最初に登場したのは、PPGWave2.3の流れを受け、MicroWaveという名前で登場したラック型の音源でした。音源方式はWaveTable方式、フィルターにカーチス製のアナログフィルターを搭載していたことによって、デジタルシンセサイザーとは思えないような暖かみもあり、太い音を放ちました。デジタルの時代に、敢えてアナログフィルターを搭載してくるところが、マニアの心をくすぐります。

PPGWave2.3は、ソフトウェア音源のPPG wave2Vとして再現されています。

microwaveの唯一の欠点として、操作するつまみを排除した2Uのラック音源だったことから、音作り、エディットが非常にやりづらく、なかなか個性がありながらも、使いこなすには時間を要するやっかいな機種でした。
サードパーティーでエディットの外部コントローラーが発売されたほどです。
YAMAHAのDXシリーズもそうでしたが、なぜかハードウェアからツマミを排除する傾向が強かった時代です。

次に登場したのは、MicroWaveIIという、MicroWaveの後継機種です。
後継機種と言っても、MicroWaveのアナログフィルターがデジタルフィルターに変わり、オペレーションもMicroWaveよりは扱いやすくなってます。音はと言えば、次に登場するMicroWaveXTとほぼ同じと思ってもいいでしょう。パッチデータもOSの最終バージョンも同じだと言うことからも、この2機種は形の違いだけで、中身はほぼ同じと言ってもいいと思います。
こちらは、ようやくmicroQ同様に、エディットが階層的に扱えるようになり、エディットが直感的に操作しやすくなりました。(わかりやすくなっただけで、操作ツマミがなく、手間が掛かるのは同様です)
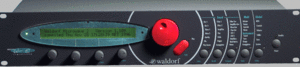
ウェーブテーブル方式のみのシリーズ最終形として、MicroWaveXTが登場します。サウンド自体は、前バージョンのMicroWaveIIと同じですが、ラック版もキーボード版のXTkも、パネルのレイアウトが大幅に変更され、サイズも2Uから4Uへと大型化しています。
wavetableのオシレータセクションと、エディットパラメータ、クイックエディット用の液晶パネル、ツマミ。
各セクションの操作ツマミノブ以外にも、液晶パネルに表示される上部パラメータに対して、下のノブで操作もできます。
この操作つまみが増えたお陰で、劇的にオペレーションがしやすくなりました。ウェーブテーブル方式の特徴でもある、エンベロープを使った波形の時間軸に沿ったモーフィング、スゥイープサウンドも、8つのエンベロープつまみで、自在にコントロールできるようになりました。
フィルターセクションと、パッチセレクトダイアルと、アンプ、LFOセクション、エンベロープセクション。
液晶表示とホイールコントローラー。
背面パネル。
この楽器は、音とは関係なくこの人目を引くオレンジの斬新なカラーも特徴的です。(光の加減によって、レビューの画像の色が異なっていることをご了承ください)出荷ロットによって、このカラーや塗装の表面質感、つまみの形状やダイヤルのカラー、はたまた、世界666台限定のブラックモデルなど、マニア心をくすぐる様々なロットがあるのも、日本の大量生産型シンセサイザーとは違うところかも知れません。

今回レビューで使用したMicroWaveXTkは、ノーマルの10ボイスではなく、拡張された30ボイスモデルです。XTには、DUALモードというものがあり、(ユニゾンモードと同意)これを使うことで、とてつもなく分厚いサウンドを発します。
10ボイスでは、DUALの場合にどうしても発音が半分の5ボイスになってしまうため、パッドサウンドなどでは、微妙に物足りなさを感じる場合がありますが、30ボイスもあれば、DUALで15ボイス使用できるので、ストレスなくプレイできます。
ただ、ノーマルでもこのXTのサウンドを聴いたら10ボイスでも十分であり、30ボイスというのはとっても贅沢な仕様だと思います。
この楽器の素晴らしい所は、アルペジエーターに向いた音を発することもそうですが、wavetableという波形をサンプルした方式にもかかわらず、アナログシンセサイザー独特の波形も搭載していること(VAシンセにもなり得る)、ノコギリ波などで音を作ったときの音の太さなど、音に対する拘りが随所に感じられる所です。
映像ではバーチャルアナログシンセサイザーであるMicroQのキーボード版(これも結構レアなんです)とともに、デモ演奏を行ってるので、ぜひともそのサウンドの分厚さと、MicroQとの音のキャラクターの違いを聴いてみてください。
最後に、このmicrowaveXTのwavetable波形までも搭載した、Waldorfの最新ソフトウェアシンセサイザー「largo」。
ハードウェア音源では、「blofeld」。
どちらのシンセサイザーも、QやmicroQのバーチャルアナログ音源と、WAVE,microwaveXTなどのwavetable音源を搭載した、waldorfがまさに現代に蘇らせたシンセサイザーです。

是非、お試しあれ!
著者: 氏家 克典